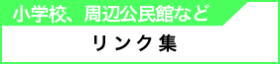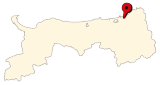つどう まなぶ むすぶ 鳥取市立賀露地区公民館
電話でのお問い合わせはTEL.0857-28-1034
〒680-0909 鳥取県鳥取市賀露町南5丁目1718-3
公民館大倉庫storage
賀露のホーエンヤ話
貝殻節は県内6か所で伝承されています。賀露では「ホーエンヤ」と呼んでいました。賀露誌には、このホーエンヤは「文化・文政年間の頃、賀露の漁師によって唄いだされた」とあります。江戸時代の漁業には磯漁と沖漁があり、賀露では貝殻漁である沖漁は許されていませんでしたので、現在の貝殻節の原型ができたのは、漁業制度が再編成された明治8年以降と考えられます。
賀露には、貝殻漁を経験された網尾一男さんが伝える貝殻節と、歌詞をアレンジしたり追分節を入れて芸術性を高めた民謡家浜沢長三郎さんの唄う貝殻節があります。長三郎さんに民謡を教えたのは、同じ賀露に住む岩本松太郎さんでした。松太郎さんを知る人は、「松太郎さんが長三郎さんに教えた貝殻節と、一男さんが歌っていた貝殻節は同じだった」と記憶されています。
ところで、貝殻節には面白い伝説があります。「亀井侯に仕える若侍が、貝柱を取る浜の娘を見るや武士を捨てて漁師となり、貝殻漕ぎを始めたが、あまりの重労働に思わず嘆声を漏らした」という話です。前述の松太郎さんを知る人にこのお話をしたところ「伝説は知らないが、昔の武士が食い詰めて漁師になり、その一家は賀露で暮らしたと聞いたことがある」とのことでした。
明治9年の秩禄処分の後、収入が閉ざされた士族の生活は困窮を極めました。新聞では無銭飲食や乞食、子女の身売りがあったと報じられていますので、この頃、士族が漁師になるというのは容易に推測できます。もしかしたら賀露の「ホーエンヤ」は、明治初期から中期にかけて士族の末裔がつくったのかも知れません。いずれにせよ賀露に住んでいた先人の想いが伝えられている貝殻節ですので、大切に後世に引き継がなければと思います。
2024年5月

大正15(1926)年 当時の賀露港の様子
【賀露伝承芸能保存会】
賀露伝承芸能保存会は、賀露に伝わる貝殻節を大切に保存し、次の世代に引き継ぎたいと想っています。
映像は昭和4年に賀露で撮影されたイタヤ貝大発生時の港の様子、唄は令和6年5月に録音しました。
賀露には、貝殻漁を経験された網尾一男さんが伝える貝殻節と、歌詞をアレンジしたり追分節を入れて芸術性を高めた民謡家浜沢長三郎さんの唄う貝殻節があります。長三郎さんに民謡を教えたのは、同じ賀露に住む岩本松太郎さんでした。松太郎さんを知る人は、「松太郎さんが長三郎さんに教えた貝殻節と、一男さんが歌っていた貝殻節は同じだった」と記憶されています。
ところで、貝殻節には面白い伝説があります。「亀井侯に仕える若侍が、貝柱を取る浜の娘を見るや武士を捨てて漁師となり、貝殻漕ぎを始めたが、あまりの重労働に思わず嘆声を漏らした」という話です。前述の松太郎さんを知る人にこのお話をしたところ「伝説は知らないが、昔の武士が食い詰めて漁師になり、その一家は賀露で暮らしたと聞いたことがある」とのことでした。
明治9年の秩禄処分の後、収入が閉ざされた士族の生活は困窮を極めました。新聞では無銭飲食や乞食、子女の身売りがあったと報じられていますので、この頃、士族が漁師になるというのは容易に推測できます。もしかしたら賀露の「ホーエンヤ」は、明治初期から中期にかけて士族の末裔がつくったのかも知れません。いずれにせよ賀露に住んでいた先人の想いが伝えられている貝殻節ですので、大切に後世に引き継がなければと思います。
2024年5月

大正15(1926)年 当時の賀露港の様子
【賀露伝承芸能保存会】
賀露伝承芸能保存会は、賀露に伝わる貝殻節を大切に保存し、次の世代に引き継ぎたいと想っています。
映像は昭和4年に賀露で撮影されたイタヤ貝大発生時の港の様子、唄は令和6年5月に録音しました。