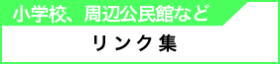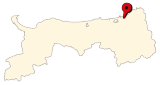つどう まなぶ むすぶ 鳥取市立賀露地区公民館
電話でのお問い合わせはTEL.0857-28-1034
〒680-0909 鳥取県鳥取市賀露町南5丁目1718-3
公民館大倉庫storage
昭和100年三大出来事in賀露 第1回 鳥取市との合併
令和7年は、「昭和が始まってから100年」という節目の年にあたります。
そこで今月号から3回にわたり、この100年間に賀露で起きた三つの大きな出来事を振り返ります。
第1回は「鳥取市との合併」です。
昭和12(1937)年、全国的な「昭和の大合併」の流れの中で、鳥取市と賀露村は合併しました。
この合併には、面白いエピソードがあります。
当時の鳥取市は産業基盤があまり強くなく、賀露村の農業や漁業、造船業など活発な経済活動に加え、鳥取港を海運の拠点として活用できることや、砂丘地の開発、畜産など、多くの可能性を秘めた賀露村の併合を強く望んでいました。一方の賀露村も、道路整備や小学校の増改築、港の整備などを望んでいました。
しかし合併条件を決めるとなると、どちらも損をしないようにと慎重になり、話は簡単には進みません。当時、合併の仲介役を務めた鳥取県のある職員は、こう振り返っています。
「双方とも相当色気はあるのに、声をかけた方が損だとばかりに、お互い自重して頑張り合っている。こうした駆け引きは、まるで青春の胸躍る男女の気持ちにも似ている。この『恋愛』、ぜひまとめてやりたいと思ったのです」
職員は、相思相愛でとんとん拍子に話が進むと思っていたようですが、現実はそう簡単ではありませんでした。合併の話が9割方進んだところで、賀露村の岸本村長が異議を唱えました。
「鳥取市にはちっとも誠意がない。全村民が憤慨しています。賀露村は従前どおり賀露村としてやっていきます」
驚いたのは鳥取市です。市の担当者は「合併には駆け引きがつきものですが、これほど大がかりな芝居は知りません。何しろ村全体が打った芝居ですから」と回想しています。
しかし単なる芝居ではありませんでした。漁業の水揚げ量は一段と増え、農業は養蚕や養鶏、砂丘地農業などの副業も本業と変わらないほど盛んになり、賀露の価値を高めたのです。
合併の評価はさておき、賀露町が一丸となって経済発展に向かっていったのは、確かな歴史です。歴史が刻んできた結束の力を礎として、町全体で心を寄せ合い、これからも歩み続けていきたいものです。

賀露村役場
そこで今月号から3回にわたり、この100年間に賀露で起きた三つの大きな出来事を振り返ります。
第1回は「鳥取市との合併」です。
昭和12(1937)年、全国的な「昭和の大合併」の流れの中で、鳥取市と賀露村は合併しました。
この合併には、面白いエピソードがあります。
当時の鳥取市は産業基盤があまり強くなく、賀露村の農業や漁業、造船業など活発な経済活動に加え、鳥取港を海運の拠点として活用できることや、砂丘地の開発、畜産など、多くの可能性を秘めた賀露村の併合を強く望んでいました。一方の賀露村も、道路整備や小学校の増改築、港の整備などを望んでいました。
しかし合併条件を決めるとなると、どちらも損をしないようにと慎重になり、話は簡単には進みません。当時、合併の仲介役を務めた鳥取県のある職員は、こう振り返っています。
「双方とも相当色気はあるのに、声をかけた方が損だとばかりに、お互い自重して頑張り合っている。こうした駆け引きは、まるで青春の胸躍る男女の気持ちにも似ている。この『恋愛』、ぜひまとめてやりたいと思ったのです」
職員は、相思相愛でとんとん拍子に話が進むと思っていたようですが、現実はそう簡単ではありませんでした。合併の話が9割方進んだところで、賀露村の岸本村長が異議を唱えました。
「鳥取市にはちっとも誠意がない。全村民が憤慨しています。賀露村は従前どおり賀露村としてやっていきます」
驚いたのは鳥取市です。市の担当者は「合併には駆け引きがつきものですが、これほど大がかりな芝居は知りません。何しろ村全体が打った芝居ですから」と回想しています。
しかし単なる芝居ではありませんでした。漁業の水揚げ量は一段と増え、農業は養蚕や養鶏、砂丘地農業などの副業も本業と変わらないほど盛んになり、賀露の価値を高めたのです。
合併の評価はさておき、賀露町が一丸となって経済発展に向かっていったのは、確かな歴史です。歴史が刻んできた結束の力を礎として、町全体で心を寄せ合い、これからも歩み続けていきたいものです。

賀露村役場