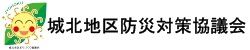防災対策協議会会長あいさつ
城北地区防災対策協議会
会長鈴木伝男
令和5年の年頭に当たってご挨拶申し上げます。
昨年度は、新型コロナウイルスの感染が、国内で初めて確認されてから3年。デルタ株から、感染の主流がオミクロン株に置き換わり、感染者数の増加が桁違いに大きくなった1年間でした。ワクチン接種も進んで、持病のない若い世代を中心に軽症で済む人が多くなった反面、第8波に入って死亡数が連日過去最多を更新しました。
この1年間、鳥取市においても感染拡大の波が繰り返し押し寄せ、これによって令和4年度通常総会は、3年間続けての書面決議となりました。
また、防災会事業の危機管理にも迫られました。当初計画していた「一時集合場所集合訓練」の実施の可否を決定しなければならない7月時点で、鳥取市には『鳥取県版新型コロナ警報』の「注意報」(西部地区:「警報」)が発令されていました。特措法に基づく「BA.5・第7波特別対策プロジェクト」への協力要請(7月7日~31日)
・鳥取市を含む7市町には「BA.5・第7波対策緊急共同メッセージ」(2022年7月12日更新)も出されていました。
この、ぎりぎりの状況の中で、7月28日に「自主防災会長会・役員会」を開催し、「集合を伴う訓練」の実施は『危険』と判断し、当初計画していた「一時集合場所集合訓練」を『中止』し、自主防災会長と役員を対象にした「公民館:避難所開設訓練(開設手順確認訓練)を実施することとしました。
ところで、コロナ禍の中、全国各地で自然災害が発生し、感染防止に配慮した避難行動の重要度を増した1年間でもありました。
3月16日深夜に発生したマグニチュード7.4の福島県沖地震。能登半島の群発地震。東北地方と北陸地方で発生した8月豪雨による土石流(新潟県村上市小岩内)。9月に発生した、中心気圧910hPaという過去最大級の「スーパー台風」が、日本列島を縦断しました。
その都度、各地域で災害発生情報として、“住民に命を守る最善の行動を求める【警戒レベル5】”が発令されましたが、迅速な避難に結びついていないのが現状でした。
この状況は、城北地区とて余所事ではなく、家族の災害関連死等を回避する上でも、これから起こるかもしれない災害に対して、家族構成や地域特性などに合わせて、災害種に沿った避難行動計画を、個々で立てておくことの大切さを住民に啓発し、命を守る迅速な避難を促すことが今後の課題だと考えます。災害対応には“正解”はありませんが、平時に“ベスト”を尽くしておく必要性を強く感じた1年間でした。
ところで、新型コロナウイルスの感染法上の位置付けが、5月8日から季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げられます。感染者の外出自粛やマスク着用、医療機関への受診など、これまでと対策が大きく変わります。
現在、オミクロン株はBA.5からXBB.1.5という新しい変異ウイルスに変化しつつあり、アドバイザリーボードの資料によれば、第7波・8波ほどは増えないまでも、5月上旬~中旬に東京都内で新型コロナの第9波のピークを迎えると試算想定されています。
このような状況下でも、いざ、災害が発生し避難所(避難場所)が開設された場合には、鳥取市地域防災計画(令和3年度修正)にそって、これまで通りの感染防止策を徹底する必要があります。
コロナウイルスは、つばなどのしぶき(飛沫)で感染が広がるインフルエンザとは異なり、飛沫に加えて、もっと微小なエアロゾル(マイクロ飛沫)で感染が拡大します。避難所には、重症化リスクのある不特定多数の方が避難してくる場所です。今後も、マスクの着用等、感染防止を呼びかける対応をとる必要があります。
本年度も、「自分の命は自分で守る(自助)」・「自分達の地域は自分達で守る(共助)」という基本的な防災力の構築が重要であると考えます。同時に、今後のコロナ感染状況等、不測の事態に備えて計画的に、粛々と出来ることから防災事業を進めていくことが肝要と考えます。
城北地区防災対策協議会は、町内単位の自主防災会・各種団体(規約:別表1)と連携調整し、防災に対する知識・技能等の啓発と、災害時の避難等のあり方について検討するとともに、訓練を通して地域住民の安全・安心を担保する地域防災力を高めることを目的に、本年度も取り組みを行います。